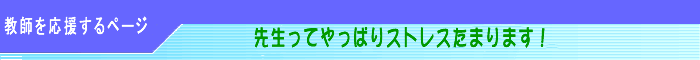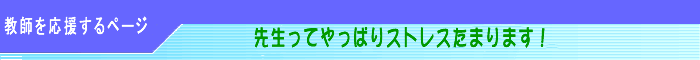|
それでは、論理情動行動療法に基づいて、教師自身のストレスについて考えてみましょう。
例えば、「生徒は教師のいうことを素直にきかなければならない。」という信念をもっている先生がいたとします。
この先生の注意に対してある生徒が素直に言うことをきかずに反抗したとします。その時その先生は、「生徒は教師のいうことを素直にきかなければならない。それなのに、この生徒は反抗した、本当にイライラする、絶対に許せない」と考えたとします。この時の先生の感情はどうなっているでしょうか。
そうですね、心から怒りを感じているでしょう。それでは、行動はどうなるでしょうか。もしかすると、イライラして体罰を加えてしまうかも知れません。体罰は今の学校では許されていませんね。
それでは、ここで「生徒は教師のいうことを素直に聞かなければならない。」という信念について考えてみましょう。「生徒は教師のいうことを素直に聞かなければならない。」と考えていると、素直に言うことを聞けない生徒にあうたびに、強いストレスを感じることでしょう。また、実際には素直に教師の言うことを聞けなくなっている生徒も多数いることでしょう。そこで、そのような現実に適応しやすい合理的な信念を考えてみましょう。
現実には、教師の言うことを素直に聞けなくなっている生徒もいるのですから、「生徒は教師のいうことを素直に聞けるにこしたことはないが、そうできない生徒もいる。そういう生徒の1人でも2人でも私たちの指導で人格が成長してくれるにこしたことはない」という信念に変えてみるとどういう感情や行動に変わるでしょうか。
「生徒は教師のいうことを素直に聞けるにこしたことはないが、そうできない生徒もいる。反抗的な生徒の1人でも2人でも私たちの指導で人格が成長してくれるにこしたことはない。」という信念を持っていて、反抗する生徒にあったとします。その時には、「生徒は教師のいうことを素直に聞けるにこしたことはないが、そうできない生徒もいる」と現実を受け入れているのですから、あまりイライラしなくてすみますね。
また、「反抗的な生徒の1人でも2人でも私たちの指導で人格が成長してくれるにこしたことはない」と考えているのですから、その生徒のことを理解してあげながら徐々に心の成長を願うという態度に変われますね。そして、「こういう生徒は叱りつけるだけでは、心が成長しないな」と考えられれば、体罰や説教だけではなく、その生徒の話を聞いて理解してあげるという姿勢にも移れるでしょう。
このように、教師自身の持っている信念を少し変えるだけで、自分自身のストレスも減り、より効果的な指導ができる先生に成長していけるのではないでしょうか。
このプログラムで論理情動行動療法と認知療法を理解していくと、自分自身のストレスを引き起こしている考え方についても再考してみることができるようになっています。
|